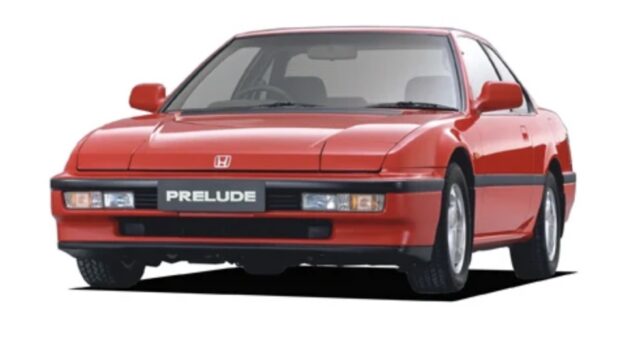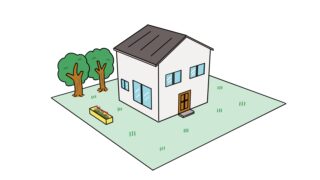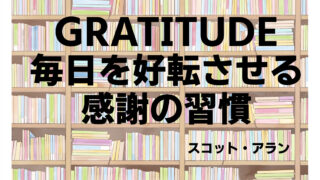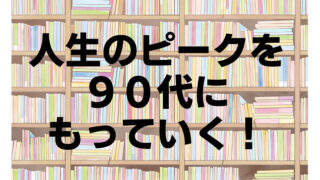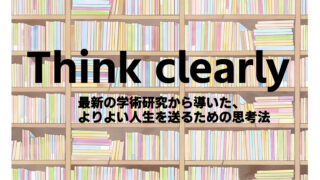HONDA 0seriesがアップデートされました
1月7日のアメリカ・ラスベガスでのCES(コンシューマ・エレクトリック・ショー 電子機器の見本市)において、HONDAのフル電動戦略である0seriesがアップデートされました。
具体的にはサルーンのデザインが洗練され、SUVが新たに登場しました。
個人的に色々とありまして、記事を書くのが今となってしまいましたが、その時の感動と感想をまとめたいと思います。
斬新なかつカッコイイスタイリングに圧倒されました
発表された2台を見た途端に、うわって声が出ました。
サルーンはもうカウンタック並みのかっこよさやないかい!
サルーンが劇的に変身したと感じました。
昨年初めて発表されたこのクルマを初めて見た時には、迷わず「カッコ悪!」って叫んでしまいました。その理由はフロントマスク。なんですか、この表情のない目(フロントライト)と馬鹿でかい口(グリル)は。正直引きました。
それが、今回発表されたモデルは、フロントライトがない!と思いきや、我々の世代の郷愁を誘う、待望のスライド式のリトラクタブルヘッドライトを採用。しかも、キリッと縦長になっています。グリルも下の方がチンスポのように尖っていてカッコよくなっている。
そうなると全体のスタイリングがもう、カッコよく見えてきます。一筆書きで書ける、段差のないスムーズなデザインは、これまでにない画期的なデザイン。正直、リアデザインはもう少しなんとかならないかとも思いますが、実はこのクルマのアイデンティティとも言えるデザイン。後端を縦にバスっと切ったデザインは、かつてのCRXのようなホンダらしいデザインともいえます。
そう思いながら、じっと見ていると、ランボルギーニ・カウンタックにしか見えなくなってきました。フロントマスク、サイドから見た流れるようなフォルム、後端が切り上がったようなフォルム。まさにカウンタックです。しかも、切れ目のない流麗なデザインはカウンタックのデザインを完全に凌駕しています。スーパーカー世代の我々にとって、カウンタックといえばその象徴と言えるクルマ、郷愁を誘うクルマなのです。
そんなスポーツカーフォルムながら、中身はその名の通りのサルーン。EVのスペース効率のメリットを活かし、4人が余裕を持ってくつろげる空間を確保しています。このギャップがまたいいのです。
これこそ、自動車界の2刀流、一粒で2度美味しいと言えます。商品魅力はずば抜けていると思います。量産化が楽しみです。
新登場のSUVも斬新でスマートなスタイリングで最高!
今回新しく登場したのがSUVモデルです。
ホンダeのような可愛らしさをどことなく残しながらも、それをスマートで流麗なSUVフォルムに昇華した印象です。
サルーンと同じように、リアデザインは後端が切り上がり縦に切ったデザイン。0シリーズのアイデンティティにしようと意図しているのがわかりました。これはこれで独特でいいと思ってきました。
両車とも、ここ数年ホンダのデザインに見られる、シンプルかつ流麗なデザインの極みといった印象。この方向性は、自分としては最高だなと思っています。
プレゼンが斬新だった!
クルマも斬新で素晴らしかったのですが、加えてプレゼンが斬新でした。
ユーザーが所有した自分をイメージできる動画
プレゼンの中で出てくる、このクルマがユーザーにもたらす世界感を表現する動画は、秀逸だったと思いました。
これを見ながら、これまでにない世界が待っていそうだなと思いました。何より、クルマが次第にユーザーに寄り添い変わっていくイメージは、すごく好感を持ちました。何か、相棒とでも言いますか、話し相手、生活を共にする家族のように、クルマが変化していくイメージを持ちました。
臨場感あふれるプレゼン
そして、プレゼンの舞台表現です。最初に思ったのは、180度ほどの大型スクリーンが圧巻でした。ホンダのやる気を表していると感じました。
特筆すべきは、自動運転のプレゼンでした。
本動画の、20:45あたりからの自動運転の具体的シーンのプレゼンが始まります。スクリーンには、実際の走行シーンが映し出され、それに応じてターンテーブルに乗った実際のクルマが向きを変えていきます。あたかも実車がそこを走っているように感じました。
自動運転の技術的な面はさておき、ユーザーが実際のシチュエーションでどういうメリットがあるかを理解しやすいプレゼンだったと思います。画期的だったし、力の入れようは半端なかったなあと感じました。
肝心なダイナミクス性能はどうなのか?
しかしながら、自分が期待しているのはダイナミクス性能。
これまでにない革新的な走りができるのではないか?と期待大です。
ホームページでのこちらの解説によると、
こんな写真がありました。引用させていただきます。

その解説がこうです。
HondaのSDVは、誰もが安心・安全に運転を楽しめることを目的に、さまざまな制御デバイスをシームレスに連動させ、操る喜びを提供するダイナミクス統合制御の実現を目指します。これまでHondaが磨き上げてきた、VSAやアダプティブ・ダンパー・システムなどのダイナミクス制御技術に加え、Honda独自のロボティクス技術で培った、3次元ジャイロセンサーによる高度な姿勢推定技術や安定化制御技術を活用。ステア・バイ・ワイヤや制御サスペンション、駆動モジュールであるe-Axleといったバイ・ワイヤ・デバイスを統合制御します。また、e-Axleによる駆動トルク制御とVSAによるブレーキ制御を協調させることで四輪の駆動力を独立かつ緻密にコントロールし、すべりやすい路面であっても気持ちよい加速を可能にします。これらにより、さまざまなシーンで車両を安定させ、意のままの挙動を実現することで、高い安心感の中で操る喜びを提供します。
さらに、ドライビングを重ねることでドライバーの特徴・技量・嗜好までを理解し、シーンに応じたドライバー好みのドライビングモードを提案したり、カメラなどのセンサーで得た外部環境情報をもとに路面状態を推定し、状況に応じたドライビングモードを提供したりするなど、ユーザー一人ひとりに寄り添いながら、軽快な乗り味や、あらゆるシーンでの安心感の提供を目指します。
電子制御ができるシステムを多く採用しながら、走る曲がる止まるの全てをシームレスに連携して、操る喜びを究極まで高めていく。
ここからは勝手な想像ですが、本家カウンタックは、ミッドシップカーであり、後輪寄りの重量配分をしています。トラクションに優れてはいるものの、ハンドリングの前後バランスで言うと、プッシングアンダーステア傾向になります。
EVのサルーンは、4輪駆動であれば、理想的な重量前後バランスを実現できます。2個のモーターの配置を前後に配置することと、バッテリーの配置でバランスを取ればです。さらにモーターを増やして、4個にすれば、4輪それぞれの駆動力を個別に制御でき、ブレーキではできないスムーズなトルクベクタリングが実現できます。そうなったら、本家カウンタックを遥かに超えた自由自在なハンドリングが実現できそうです。いやー妄想が膨らみます。楽しみですね。
これから先、自動運転の時代だと言われて久しいですが、やはりクルマは運転してなんぼだと自分は思います。しかも、自動運転のためには、走る曲がる止まるといった基本的なクルマの要素が高くなければ、ハイレベルの自動運転性能は実現できないと思います。
ですから、HONDA 0シリーズが目指すダイナミクスの方向性は、非常に頼もしく、自分にとってワクワクして待ちたいなあと思えるものでした。
最後に
HONDA 0シリーズの1発目は、今回発表されたSUVで26年前半だということです。
実車がお目見えし、試乗ができる日を心待ちにしたいと思っています。