今後の自動車業界はどうなっていくのか?
ふと、自動車業界から離れた自分にとっても心配になってくるものです。でも不安である反面、これから世界がどんなふうに変わっていくのかというワクワク感と期待感を含めて、未来に好奇心を持っていたのでした。
そして見つけたこの本。
題名:Mobility X
シリコンバレーで見えた2030年の自動車産業
DX,SXの誤解と本質
著者:木村 将之/森 俊彦/下田裕和
発行:日経BP
この本を読んで、今まで自動車開発にのみ集中してきた自分にとって、世にいう「100年に一度の変革期」という言葉をやっと理解できた気がしますし、まさに「産業界の変革期」とも言える時期だということ、新しいもの、ワクワクする未来が誕生するために、現役の技術者たちが日夜頑張っているんだなと思いました。
結論
本書に紹介されている企業に共通して言えることは、「顧客の価値や体験をとことん第一に考えて提供しようとしている」ということ。それを実現するために叡智を結集して創造的な仕事をしているということでです。
その考え方をベースに、既成の概念をひっくり返す柔軟な発想で、今までの常識をあっという間に覆していく。まさにゲームチェンジ。これから10年ちょっとで、あっという間に産業構造や世の中が一変してしまうような変革期にいることがよく理解できました。

そして、日本の未来に光が刺すかどうかは、凝り固まった旧態依然とした日本の製造業が、この潮流にどのように対応できるのか?変革していけるのか?にかかっていると思います。この潮流を正しく理解して、日本の企業としてできうる役割を見つけ、しっかりまっとうしていくことが大事だと思いました。
また、元自動車エンジニアとして感じるのは、現代のエンジニアが取り組むテーマが、自動車というよりも、本書の題名にあるような次世代モビリティの創造というスケールの大きい仕事であり、新鮮でワクワクする仕事ばかり。こういう仕事ができる今の時代の彼らは羨ましいなあと感じたし、こんなチャンス滅多にない時代だと思うので、大いに活躍して欲しいと思いました。

近年よく聞く言葉たち
そんな話をする前に、本書にも登場する近年よく聞く言葉たちを再度確認しておきます。
CASEとは?
ここ最近の自動車業界での流行り言葉、キーワードとなっているCASE。これは、モビリティサービスの技術やサービスの潮流を表し、今後の自動車業界の方向性を示す言葉です。
C:Connected つながることでのソフトウエアの高頻度の提供が可能となっている
A:Autonomous 自動運転技術によるロボタクシーサービスなどへの展開
S:Shared ライドシェアサービスへの展開
E:Electric 自動車の電動化
これらは、顧客の価値を最終目的とする中で、それを達成するために自動車業界で今後やっていかなければならない技術、手段、方法論であると思います。
顧客の価値を想定した上で、これらのものを掛け合わせて、いろんなサービスを具現化していくことになります。
DXとSX
二つのトランスフォーメーション、つまり転換についての言葉で、こちらも最近よく聞く言葉である。「顧客の価値・体験」という目的を実現するための考え方ではあるものの、CASEよりは、もっと上流の言葉であると思います。
DX 顧客体験から目をそらさない
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の意味。
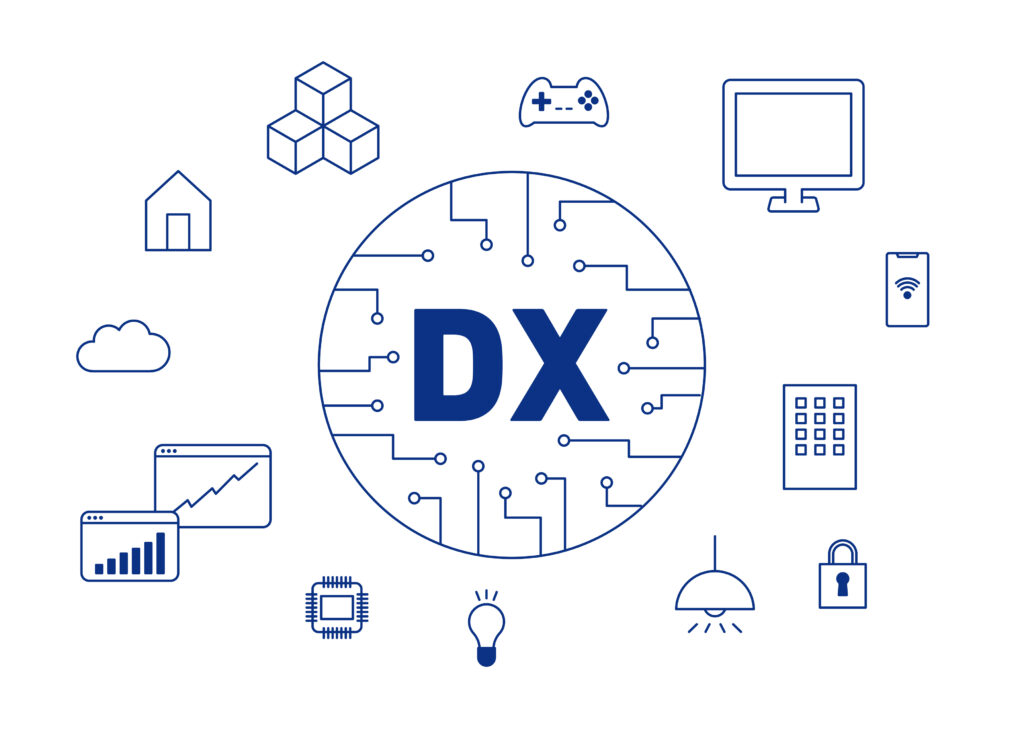
顧客の価値・体験を主眼に置く開発の中で、サービスや商品を開発していく上で元になる顧客データを収集・分析するためにデジタル化を促進することを意味しています。
顧客の特性を活かして、こんなサービスまで考えついたのか!こんなところまでやってくれるのか!と驚くばかりのサービスが今後どんどん現れてくる気がしてきますね。
SX 脱炭素社会に向けた企業の取り組み
SXとは「サステナビリティートランスフォーメーション」の意味。
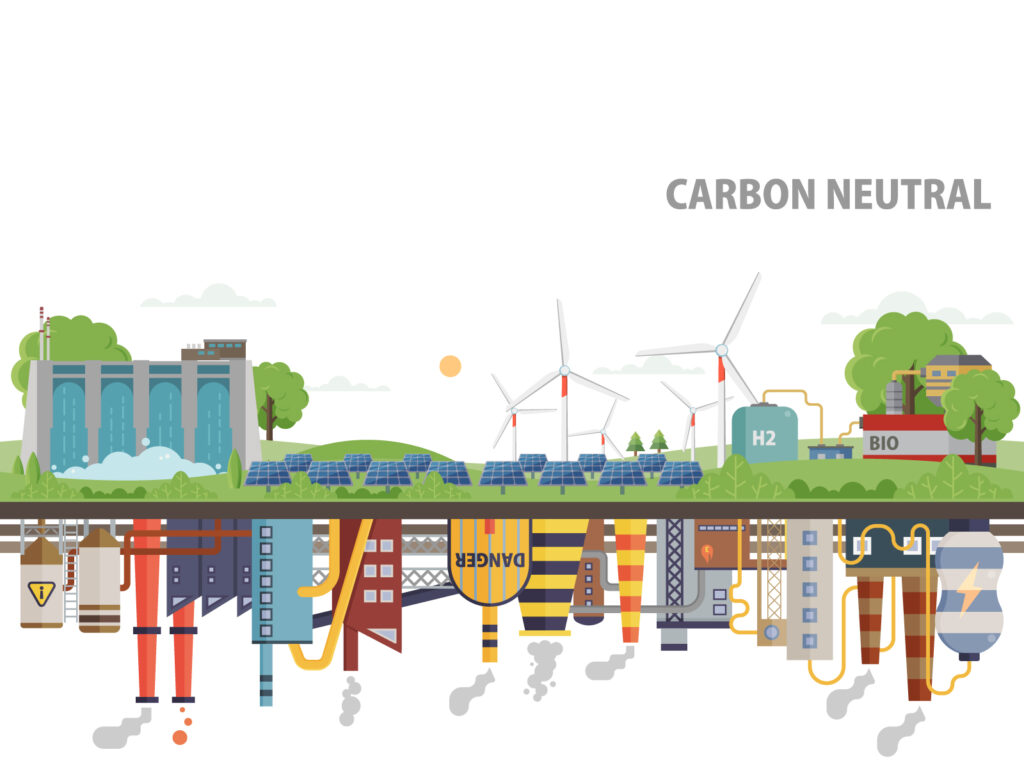
地球環境問題への対応、脱炭素化の重要性を語る言葉である。今や避けては通れない規定演技以上のものになりつつあり、コーポレートガバナンスやコンプライアンスと並ぶ、企業を評価する上で重要な要素となりつつあります。
またそのサービスや商品を選ぶ上での1種のアドバンテージとも言える要素ともなりつつある。そして顧客がそのサービスを利用することで脱炭素に貢献できることに対する価値も上がりつつありますね。
各社の驚くべき取り組み
本書には、DX/SXの本質を理解し展開する企業が紹介されています。
その中でも、自分が今まで知らなくて、こんなこと考えていたのか!!と驚いた取り組みについてピックアップして紹介したいと思います。

【Uber】
Uberという企業を表現するにぴったりな言葉が本書にありましたので、引用させていただきます。
ウーバーは顧客の視点に立ち、「安い」「便利」「早い」「安全」という顧客が求めるすべての面において、最新のデジタルテクノロジーを駆使して様々なサービスを立ち上げ、新たな顧客体験を創造している。(P35)
自分が感じたのは、人やモノに対する移動に求めるものに対して、顧客の気持ちをくすぐるサービスだなと思いました。
そんなUberの驚くべき取り組みを紹介します。
配車アプリに見る工夫
顧客の気持ちを第一に考えた工夫が、配車アプリに注ぎ込まれています。
・顧客をイライラさせない工夫として、クルマの到着予定時間や現在位置をアプリ上で表示
・安心して乗車できるように、事前に料金を提示する。まさに明朗会計である。
・顧客が乗車後に、ドライバーの評価をし、評価が低いと運転機会を得られないという。
本当に顧客の気持ちを深掘りして作り上げたアプリであることがよくわかりますね。
自分は、Uber eatsでからやまの唐揚げをよく発注しますが、同様に配達のライダーの方の現在位置や到着予定時刻を逐次見ることができるため、多少時間が前後してもこちら側の心の準備ができましたし、安心感はありました。
日本では、配車サービスとしては、Uber taxiと称した、タクシーを配車するサービスしか無いようですね。タクシー業界が強く、個人が参入してくると、商売あがったりになるためですね。そんな日本の既得権益や、昔ながらの時代遅れの考え方を守ろうとする姿勢が、日本の未来への歩みを遅くしている気がしますけどね。ロボットタクシーの時代なんかすぐ来てしまうかもしれませんよ。そうしたら彼らはどうしていくんでしょうか?
画期的な乗り合いの仕組みを発想
Uberは、運賃をできるだけ抑えるために、乗り合い乗車可能なサービスを提供しています。しかし、従来までは、前に乗車している人の走行ルート上に、後から乗合する人が現れることがそれほどなく、乗り合いが成立しないという課題があったとのこと。
それに対して、アプリ上で後から乗合する人が指定されるポイントまで歩くように促したり、マッチングするための時間を5分程度まで伸ばして機会を増やしたりの工夫を追加し、その課題を解決したといいます。
「こんなとこ困っているんだったら、こうすればいいんじゃない?」って会議で発言している社員の姿が目に浮かびますね。発想力豊かな会社の社員は、湯水の如くあちこちに素晴らしい発想が出てくるイメージがあります。それだけ課題に対してポジティブに真剣に楽しく向き合って仕事していると言えますね。
「後から乗合する人が少なければ、歩かせて増やせばいい」という柔軟な発想で課題をクリアし、顧客のニーズである安い運賃の実現に貢献する。素晴らしくも、達成感のある仕事をするものである。
稼ぎたいドライバーの気持ちにも寄り添う
顧客だけではなく、ドライバーの気持ちも考えて対応するのがUber。
ドライバーのアプリに顧客の需要の多さを表示するようにして、儲かる地域を知らせることにしている。このことで、稼ぎたいドライバーをその地域に誘導することができる。
ドライバーの心理までもうまく操ってしまい、顧客の満足を達成してしまう、すごい企業ですね。
ダイナミックプライシングの採用
顧客の乗車するしないの判断を元に価格を決めているのではないか?という話もあります。
料金を表示した後に乗車しなかった顧客は、自社のサービスに満足せずに他社のサービスを利用したのではないか?と推定して、次回の料金を下げるようにしているのではないか?という話です。
AIを使った推定であろうが、料金設定について顧客の判断をくすぐるような料金設定をしてくる。なんとも言えん踊らされているような気もしてきますが、使ってみて心地よければ次も使うでしょうという人間の心理をついたサービスとも言えますね。
【GM】
既存の自動車メーカーでありながら、DXによる新たなビジネスを開発するのがGM。特に自動運転技術による「ロボタクシー」は、既存の移動の価値観を破壊する革新的なビジネスと言っていいと思います。
「様々な体験を演出する空間に移動がついてきている」
この言葉は、ロボタクシーの革新的な考え方を物語っている。
自動運転技術が不可欠な要素ではあるが、実現できた前提で、ロボタクシーの中で、いかに過ごすか?どんな体験価値を提供できるか?に焦点が移りつつあるという。
それは、ソフトウエアのみならず、ロボタクシー自体のハードウエアにおいても、体験価値の実現のためそれに特化したクルマ作りをしているというのだ。
もう徹底した顧客体験の具現化と言えますね。
【テスラ】
「テスラは電気自動車のメーカーである」というのは間違ってはいないが、この企業の規模からして全く不十分な表現であり、その枠を超えた企業へと巨大化しつつあると感じました。
「タイヤを付けた洗練されたコンピューター」
イーロン・マスクが15年前からのモデルSのことをこう呼んでいたそうです。スマホのアプリが随時アップデートされるのと同様に、クルマのシステムや機能が随時アップデートされていき、どんどんクルマが進化していく。
既存の開発は、製造業として自社のハードを売るためのソフトウエア開発があったものだが、テスラの考え方は逆転の発想で、顧客の価値サービスを実現するために最適なハードウエアを開発するというもの。
この考え方は革新的ではあるものの、冷静に考えると顧客重視という本来あるべき考え方であるとも言えます。既存の自動車企業はこの転換に対応するべきであるとわかっているものの、旧態依然とした今までの体制から大きく転換することはかなり難しい作業となることは明白でしょう。
そういった従来にない革新的なクルマ開発をテスラは行っているということが言えます。
ぶったまげた!!「稼げるクルマ構想」
自動運転開発も当初から積極的に取り組んでいるテスラ。
本書には、こんなぶったまげた構想をイーロンマスクがTwitterで語ったことが書かれています。
自動運転を実現した暁には、自分のクルマが勝手にロボタクシーになって稼いでくれると。
いやーこの発想は革新的すぎて、自分としてはぶっ飛びました。クルマを所有しているだけでお金を稼いでくれるという発想。凄すぎですし、素晴らしいです。顧客に対する商品価値は爆上がりではないかと思います。
そんな未来が本当に来たら顧客側ももう発想を転換しないとついていけなくなりますね。もう所有の概念を転換しまわないと。自分のクルマを所有しているというより、投資のためのレンタカーを所有しているという感覚でしょうか?
保険の概念も変わりそうです。ロボタクシーとして働いている時に事故が起きれば、クルマ自らが事故の証拠を残せる多くのカメラなどによるドライブレコーダーの強化も必要となってくるでしょう。
すごいことを考えるテスラは、まさに革新的な会社です。
テスラの狙いは、エネルギー産業であること
そして、テスラは自動車企業という枠に留まらないスケールの大きさがあります。
テスラの企業ミッションは、「世界の持続可能エネルギーへのシフトを加速すること」だといいます。これはまさに、テスラの狙っている本命がエネルギー産業であることに他ならないということを意味する。
EVやバッテリーのみならず、エネルギー貯蔵ソリューション、ソーラーパネルや関連システムなど、電気エネルギー供給の領域にも踏み込み、エネルギー産業となろうとしているのです。
脱炭素社会に向けた、効率の良いエネルギー消費を考えた場合、クルマ単体だけではなく、電気エネルギー供給環境についても包括的に考えないと実現できないと考えたテスラは、まさにそれを実行するという宣言を企業ミッションに表しているのです。
アメリカの企業らしく、脱炭素化という社会正義をかざして、勇気を持って自らの守備範囲を広げ、積極的に実行していく姿勢は、潔いとも感じます。日本において、既得権益やしがらみばかりある状況で異なる業界に乗り込んで実行していくなど、できる企業があるのだろうか?と思ってしまいます。
【Amazon】 物流業界の垂直経営でゲームチェンジを狙う
本書に、アマゾンを象徴する文章があったので引用させていただきます。
ものの移動を制し、車と家の体験を統合し始めたアマゾンは顧客の体験を第一に考え、次々とサービスを構築、産業の壁を超えている。今後様々な産業と接点のある物流というファンクション産業をテコに、進出した産業においても様々なサービスを開発していくだろう。ヘルスケアとの関連でも、調剤配達にとどまらず、顧客のヘルスケアに対するニーズを収集して強みを生かしていくと思われる。(P182)
顧客に提供するサービスや商品で、顧客との接点を数多く持ち、得られたデータで、さらなるサービスを生み出す。
計り知れない意欲を感じますね。それも金儲け優先という感覚、何か嫌らしいと感じることはは微塵にありません。それは、顧客の体験に愚直にまでフォーカスして企業活動しているのがよく分かるからですね。
期待する日本企業
本書にある代表的な企業はいづれもアメリカの企業でした。前述のように、日本の企業が顧客の体験価値を目的に考えて今ある制約や都合や既存の考え方を捨てて商品やサービスを有無出していけるのか?難しい課題だと思います。
どうしても、日本人は、制約や都合や既存の考え方で発想を制限してしまいがちですからね。でももうそんなことは言っていられませんし、言っていたら、あっという間に何周も周回遅れになってしまいますから。少なくとも、同じ周回でレースできるレベルにまで持っていきたいですね。

それを実現できる日本の企業として、自分が今浮かぶのは、以下の二つの企業になります。
トヨタ(Woven City)
トヨタが未来のモビリティのために建設しているのが「Woven City」。
こちら(トヨタ ウーブンシティ)のホームページから引用させていただきますと、
かつてトヨタ自動車東日本の東富士工場があった「ものづくり」の地に築く、未来の幸せの量産につなぐ「モビリティのためのテストコース」。 2024年夏に第1期の建物が完成予定。 その後は2025年の一部実証開始に向け準備を進めていきます。
だそうです。
電気自動車を筆頭にその他のモビリティとそれを繋ぐ都市の在り方、サービスを考えて作り上げていく実証実験の町と言えると思います。
制約を取っ払って自由な発想でより良いものより良いサービスが生まれてくることを期待せざるを得ません。
ソニーホンダモビリティ
そして次に期待するのが、ソニーとホンダが出資する電気自動車(EV)の会社「ソニー・ホンダモビリティ」です。
ソニーが生み出す画期的な車内体験価値を実現するためのクルマ作りをホンダの技術と融合しながら作り上げていく、まさにテスラのクルマ作りの実現ではないかと思います。
いくら革新的なホンダといえども、従来からの自動車メーカーですから、異文化であるソニーとの相互理解した上で、顧客の体験価値の具現化というターゲットに対して、一枚岩になることができたら、テスラに近づける日本におけるトップランナーになるのではないのか?と期待しています。
この2社の動向は今後注視していきたいなと思います。


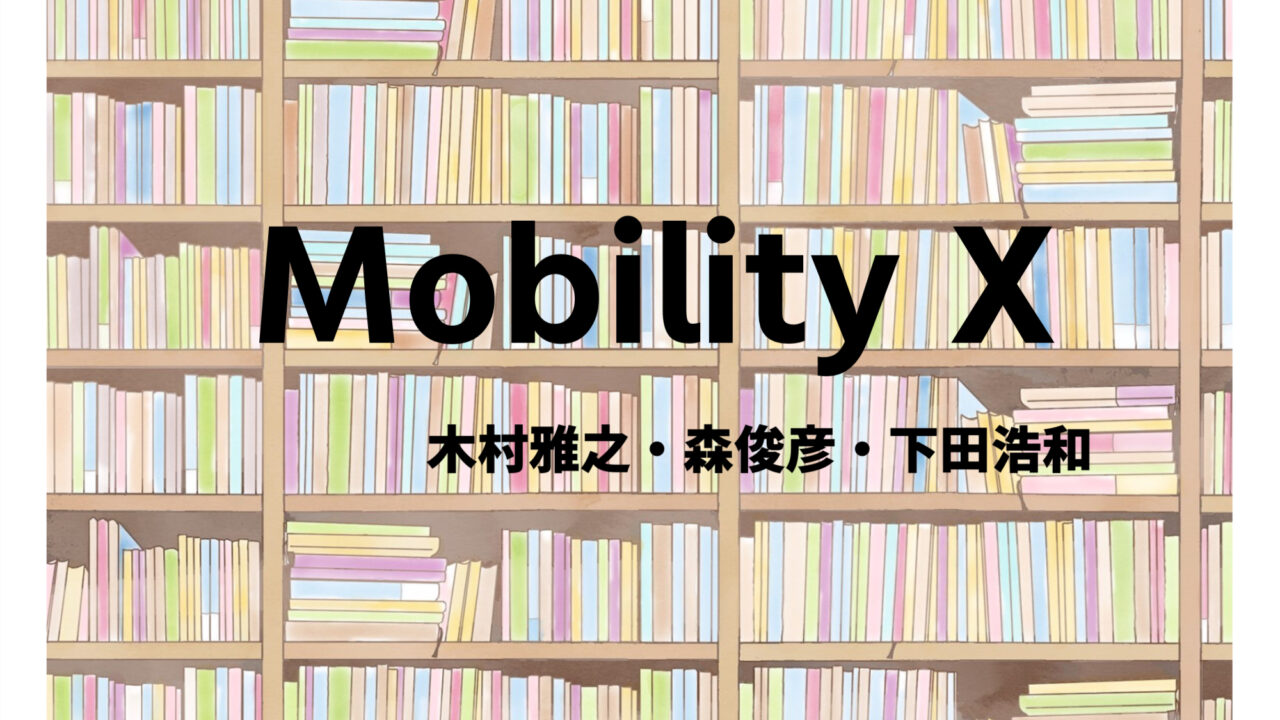



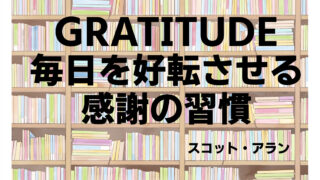







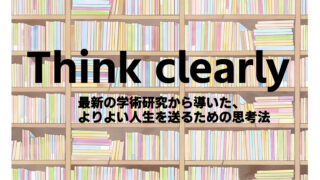

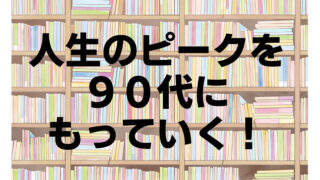





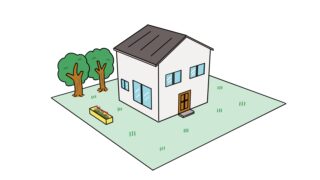






[…] きっとワクワクする未来が来るぞ!!【「Mobility X」を読んで】今後の自動車業界はどうなっていくのか? ふと、自動車業界から離れた自分にとっても心配になってくるものです。でも […]